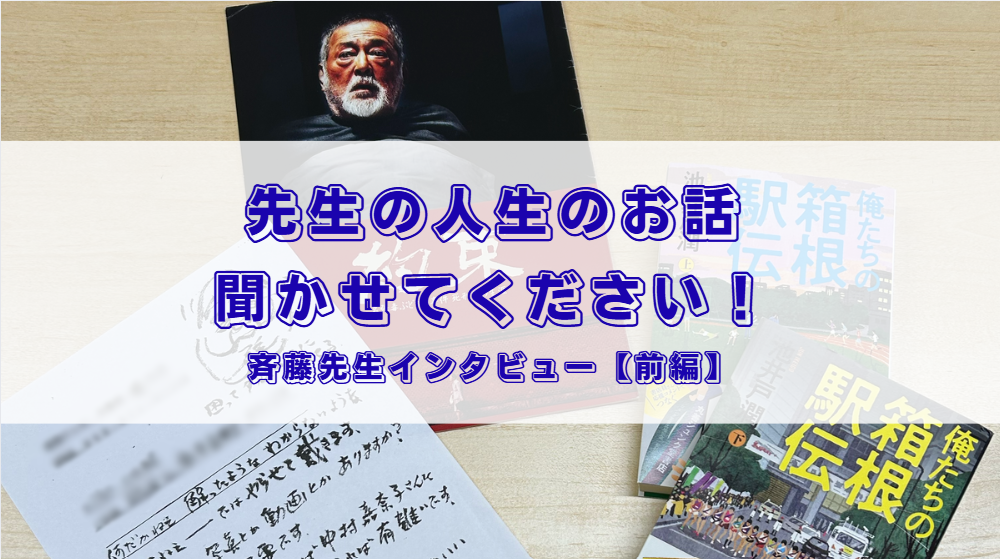
大学生活は社会に出る前の大切な時間であり、将来について不安を抱える学生も多いのではないでしょうか。
私自身も、大学4年間をどう過ごすべきか、日々考えながら学生生活を送っています。
今回は、関西大学出身でテレビ局での仕事を経験し、現在は教員として母校に戻ってきた社会学部の斉藤先生にインタビューしました。
学生時代から現在に至るまでの人生経験や、そこから得た学びについてお話を伺っています!

関西大学社会学部メディア専攻
斉藤 潤一 教授
≪専門分野≫
・映像ジャーナリズム
・ドキュメンタリー
学生時代は、ほぼ「バレーボール」だった
先生の学生時代を一言で表すなら、「バレーボール中心の4年間」である。
現在の社会学部メディア専攻の前身である、マス・コミュニケーション学専攻に所属していたものの、本人は冗談交じりにこう振り返る。
「卒業して大学は何学部だったかと聞かれると社会学部じゃなくて『バレーボール部です』って答えますね」
中学から続けてきたバレーボールを、大学でも体育会で続けた。
練習は月曜日以外ほぼ毎日。長期休暇も例外ではなく、アルバイトをする余裕もなかったという。


↑左から2番目が斉藤先生
それでも続けられた理由は単純だった。
「バレーが好きだったし、仲間にも恵まれていました」
同期や先輩、後輩と一緒に、同じ目標に向かって取り組む時間が何より楽しかったと語る。
「みんなでつくる」楽しさは仕事にも繋がっている
先生がバレーボールの魅力として挙げるのは、団体スポーツであるという点だ。
「個人スポーツよりも、みんなで1つのところに向かう方が自分には合っていました」
この感覚は、のちに携わることになるニュース制作の仕事にも通じている。
1つの番組をつくるために、記者、編集、カメラマン、照明、アナウンサーなど、多くの人が関わる。
夕方のニュース番組では、100人以上が一つの放送を支えていたという。
「放送が終わって『終了ですー!』って声がかかった瞬間、今日もやり切ったなっていう達成感がありました」
個人ではなく、チームで何かを作り上げる喜び。その原点は、学生時代の体育館にあった。
思い描いていた報道とは違うスタート
新聞ジャーナリズムを扱うゼミでの学びが記者を志すきっかけとなり、その思いを胸に名古屋の東海テレビに就職。
報道部で取材やリポートをすると期待していたが、営業の部署に配属され、理想とは異なる現実に肩を落とした。
「こんなはずじゃなかった」この時はそう思いましたが、営業の経験は後の仕事の基盤になっていました
営業では日本の社会や経済の仕組みについて知る機会が多く、人と向き合う姿勢の大切さを特に学んだという。
そこでまずは社会人としてのキャリアを積もうと発想を切り替え,人との信頼を何より重要視して仕事に熱を注いだ。
そして、入社9年目にして待ち望んだ報道部に異動。

お金を稼ぐ営業とネタを稼ぐ報道。対象は違うものの、共通点は「信頼関係の構築」にあった。
報道の仕事においても「どうしたら自分を信頼して託してもらえるか」が大切だったと先生は語る。
営業で培った人との向き合い方は、遠回りに見えて、後の報道の仕事へと確かに繋がっていた。
大学教員への転機は「もう一度、現場で作りたい」から
報道部で警察担当、行政担当を経験し、ドキュメンタリー制作にも携わるなどキャリアを重ねる中で、次第に現場から離れ、管理職のポジションに就いた。
そこから7年が経ったコロナ禍のさなか、関西大学から教員の打診を受け、今後のキャリアについて考えるようになった。
テレビ局の仕事への愛着は強かった。
一方で、母校でメディアを学ぶ後輩たちと映像制作をしてみたいという思いも次第に芽生えていった。
安定した立場を手放すことになる転職は大きな決断であり、当時は非常に悩んだという。
「転職は人生の転機やタイミングのようなものだと思っています。私にとっては、まさにその時だったのでしょう。後悔は全くなく、学生と一緒にもう一度モノづくりができることを、とても楽しんでいます」
こうして、自分が本当にやりたいことや価値観に正直に向き合い、関西大学の教員としての新たな道を選んだ。
いかがでしたでしょうか。
ここまで、学生時代のバレーボール、理想とは異なる社会人生活、そして大学教員という選択についての話でした。その歩みの中で、先生の価値観を大きく変えた「人生の転機」となる出会いがあったそうです。
後編では、その出会いとともに、今も大切にしている人生の指針、そして学生へのメッセージについて伺います!



